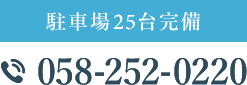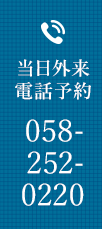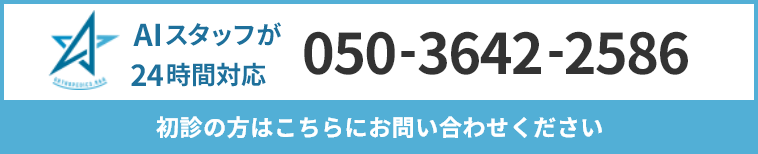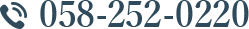高齢期の「転倒」はなぜ危険?専門医が教える予防の極意と安全な筋力トレーニング
「ちょっとした段差でつまずいた」「急に足がもつれてヒヤリとした」—高齢期の転倒は、一過性の事故ではありません。それは要介護状態への入り口であり、生活の質(QOL)を大きく低下させる最も重大なリスクの一つです。
転倒によって引き起こされる骨折(特に大腿骨近位部骨折)は、長期入院や手術を必要とし、多くの方がそのまま寝たきりへと移行してしまいます。しかし、転倒は決して避けられない「老化現象」ではありません。適切な知識と予防策、そして継続的な筋力・バランス訓練で、そのリスクは大幅に減らすことができます。
岐阜市のあおと整形外科クリニックでは、日本整形外科学会専門医である院長と理学療法士が連携し、科学的根拠に基づいた転倒予防と安全な運動器リハビリテーションを提供しています。
高齢期に転倒リスクが高まる3つの主な要因
高齢者が転倒しやすい背景には、加齢に伴う複合的な身体機能の低下があります。
1. 運動機能の低下:筋力・バランス能力の衰え
転倒の最大の原因は、足腰の筋力の低下、特に太もも(大腿四頭筋)とふくらはぎ(下腿三頭筋)の筋力低下です。これらの筋肉は、段差を乗り越える力や、バランスを崩した瞬間に踏みとどまる瞬発力を担っています。 また、平衡感覚や、足の裏から地面の情報を得る固有受容感覚が鈍くなることも、小さな傾きに気づきにくくなる原因です。
2. 骨の脆弱化:骨粗しょう症との深刻な関連
高齢者、特に女性は骨粗しょう症を患っているケースが多く、骨密度が低下しています。転倒自体は予防できても、万が一転んでしまった場合に骨折するリスクが極めて高くなります。 骨折を機に活動量が低下し、さらなる筋力低下を招くという**「負の連鎖」を断ち切るには、転倒予防と同時に骨を強くする治療(骨粗しょう症治療)**が必須です。
3. 視覚・内科的要因と環境要因
遠近感の低下や白内障などの視覚の衰えは、足元の障害物を見落とす原因になります。さらに、服用している薬(睡眠薬、降圧薬など)によるふらつきやめまい、血圧の急な変動などもリスクを高めます。加えて、ご自宅の危険な段差や滑りやすい床といった環境要因も深く関わっています。
【セルフチェック】あなたの転倒リスク度を測る
以下の項目のうち、いくつ当てはまるかチェックしてみましょう。当てはまる項目が多いほど、転倒のリスクが高いと考えられます。
|
1. 過去1年間に転倒したことがある |
|
|
2. 立ち上がる時や歩き始めに膝や股関節が痛むことがある |
|
|
3. 杖や手すりがないと歩行に不安を感じる |
|
|
4. 片足立ちを5秒以上続けることができない |
|
|
5. 医師から骨粗しょう症の診断を受けている |
|
|
6. 家の中に段差や電気コードなど、つまずきやすい場所が多い |
|
|
7. 散歩や外出の機会が週に3日未満である |
|
|
8. 複数の薬(5種類以上)を服用している |
チェックが3つ以上ついた方は、整形外科専門医による詳細な検査と、専門的なリハビリテーションを受けることを強くおすすめします。
専門医が推奨する転倒予防のための安全なトレーニング
転倒予防には、筋力(特に下肢)とバランス能力を同時に鍛える運動が最も効果的です。無理なく、毎日継続できることから始めましょう。
1. 椅子を使った太ももの筋力アップ(大腿四頭筋)
目的: 立ち上がりや階段昇降に必要な膝周りの筋肉を強化します。
- 深く座らず、背筋を伸ばして椅子に浅く座ります。
- 片方の足をゆっくりと持ち上げ、膝をピンと伸ばしきった状態で5秒間静止します。太ももの前面に力が入っているのを確認します。
- ゆっくりと下ろし、逆の足も同様に行います。 (左右それぞれ10回を1セットとし、無理のない範囲で2〜3セット行いましょう。)
2. かかと上げ(ふくらはぎ・下腿三頭筋)
目的: 歩行時の蹴り出しと、バランスを調整する能力を高めます。
- 壁や安定した家具に両手を添えて立ちます。
- ゆっくりと、できる限りかかとを高く持ち上げます。
- 上げた状態で2〜3秒間キープし、ゆっくりともとに戻します。 (10回を1セットとし、ふらつきに注意しながら行いましょう。)
3. 片足立ち訓練(バランス能力・体幹)
目的: 転びそうになった時に踏みとどまる、片足で体を支える能力を養います。
- 壁や手すりのそばに立ち、すぐに手を添えられるようにします。
- 片方の足を床から離し、30秒間を目安にキープします。
- 慣れてきたら、手を壁から少し離したり、目を閉じたりして難易度を上げてみましょう。 (左右交互に、必ず安全を確保して行います。もし30秒が難しい場合は、目標時間を短く設定しましょう。)
あおと整形外科クリニックが行うトータル転倒予防サポート
転倒予防は、単なる筋力トレーニングだけで完結しません。当院では、専門医と理学療法士が連携し、以下のような多角的なアプローチで、岐阜市の皆様の安全で活動的な生活をサポートします。
1. 正確な評価と診断
- ◼︎詳細な問診・視診
- 転倒時の状況、歩行パターン、生活環境を詳しくお伺いします。
- ◼︎画像検査(X線、エコー)
- 膝や股関節の変形性関節症の有無や、過去の骨折の痕跡などを確認します。
- ◼︎骨密度検査
- 転倒による重症化リスクを評価するため、骨粗しょう症の有無を正確に診断し、必要に応じて治療を開始します。
2. 専門的なリハビリテーション(運動器リハビリテーション)
国家資格を持つ理学療法士が、医学的根拠に基づいたリハビリテーションを提供します。
- ◼︎個別運動療法
患者様一人ひとりの筋力、柔軟性、歩行の安定性を評価し、オーダーメイドの運動プログラムを指導します。特に、日常生活動作(立ち座り、階段昇降)に直結する機能の改善に重点を置きます。 - ◼︎歩行・姿勢指導
- 転倒に繋がりやすい歩行のクセや姿勢の偏りを修正し、安定した歩き方を習得できるよう指導します。
- ◼︎装具療法
- 足底板(インソール)やサポーターなどを活用し、足元のアライメントを整え、負担を軽減します。
3. 骨粗しょう症治療と生活指導
骨密度が低い方には、骨吸収を抑えたり、骨形成を促したりする薬物療法を積極的に行い、骨折のリスクそのものを軽減します。また、ご自宅の環境整備や、適切な栄養摂取、服薬管理に関するアドバイスも行います。
院長からのメッセージ:転倒不安を安心に変えるために
転倒の不安は、知らず知らずのうちに活動範囲を狭め、心の健康までも蝕んでしまいます。私たちの目標は、ただ転倒を防ぐことではなく、自信を持って外に出かけられる、活動的な毎日を取り戻していただくことです。
「年のせい」だと諦めず、その一歩を踏み出す勇気を持って、私たち専門医にご相談ください。安全と安心を土台とした健康な毎日を、一緒に築いていきましょう。
監修者情報
監修:日本整形外科学会専門医 青戸 寿之(あおと整形外科クリニック 院長)