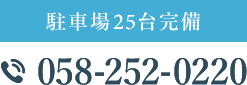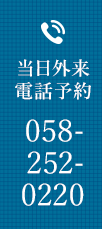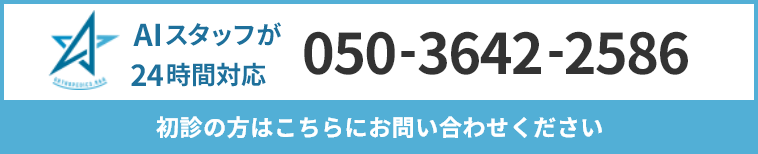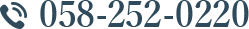「親指を動かすと手首が痛い」「タオルを絞るのがつらい」「赤ちゃんを抱っこすると激痛が走る」――もし、あなたがこのような症状に悩まされているなら、それは「手首の腱鞘炎(けんしょうえん)」、特に「ドケルバン病」かもしれません。
ドケルバン病は、手首の親指側にある腱と、その腱を包む「腱鞘(けんしょう)」というトンネルのような組織に炎症が起きることで発症します。日常生活で手や指を酷使する方に多く見られ、特に女性に多い傾向があります。
もし、この手首の痛みで日常生活に支障が出ている、仕事や育児に集中できないと感じているなら、私たち整形外科があなたの力になれるかもしれません。あおと整形外科クリニックでは、患者様一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせた丁寧な診断と治療を通じて、痛みからの解放、そして快適な日常を取り戻すサポートをいたします。
ドケルバン病とは?なぜ手首が痛むのか?
ドケルバン病は、正式には「狭窄性腱鞘炎(きょうさくせいけんしょうえん)」の一種で、手首の親指側に位置する2つの腱(短母指伸筋腱と長母指外転筋腱)と、それらを覆う腱鞘に炎症が生じる病気です。
ドケルバン病が起こるメカニズム
私たちの手や指は、腱という紐のような組織が筋肉の力を骨に伝え、関節を動かすことで機能しています。この腱は、スムーズに動くように「腱鞘」というトンネル状の組織の中を通っています。腱鞘は、腱が骨から浮き上がらないように押さえつけ、摩擦を減らす役割をしています。
しかし、手首や親指を使いすぎると、この腱と腱鞘の間で摩擦が生じ、炎症が起こります。炎症が続くと、腱鞘が厚くなったり、腱自体が腫れたりして、腱が腱鞘の中をスムーズに滑ることができなくなります。その結果、動かすたびに引っかかりや痛みが生じるようになるのです。
特に、ドケルバン病では、手首の親指側にある「第1背側コンパートメント」という狭い腱鞘の中で炎症が起こりやすく、この部位に特有の痛みを引き起こします。
ドケルバン病になりやすい人
ドケルバン病は、以下のような特徴を持つ方に多く見られます。
- ◾️女性
- 特に妊娠中、出産後、授乳期の女性や更年期の女性に多く発症します。これは、ホルモンバランスの変化が腱鞘の炎症に関与すると考えられているためです。
- ◾️手や指をよく使う仕事や趣味を持つ人
- パソコン作業(マウスやキーボードの操作)
- スマートフォンの長時間使用(特に親指でのフリック入力など)
- 美容師、調理師、医療従事者など、手先を使う職業
- テニス、ゴルフ、バドミントンなど、手首や親指を酷使するスポーツ
- ◾️育児中の親
- 赤ちゃんを抱っこする、授乳する、おむつを替えるなど、親指を広げたり手首をひねったりする動作を繰り返すことで、手首に大きな負担がかかります。
- ◾️特定の病気を持つ人
- 関節リウマチや糖尿病のある方も、腱鞘炎を発症しやすい傾向があります。
ドケルバン病の主な症状
ドケルバン病の症状は、手首の親指側の痛みが特徴的です。
- ◾️手首の親指側の痛み
- 特に親指を広げたり、動かしたりする際に、手首の親指の付け根あたりに鋭い痛みを感じます。
- ◾️腫れやしこり
- 痛みのある部分に、腫れや、触ると硬いしこりのようなものが感じられることがあります。
- ◾️動作時の痛み
- 物をつかむ、握る、持ち上げる動作
- タオルを絞る動作
- ドアノブを回す動作
- 赤ちゃんを抱っこする動作
- スマートフォンの操作
- キーボードやマウスの操作
- ◾️しびれや放散痛
- 症状が進行すると、痛みが親指や前腕に広がったり、しびれを感じたりすることもあります。
これらの症状は、日常生活の様々な場面で不便や苦痛をもたらし、QOL(生活の質)を著しく低下させる可能性があります。痛みを我慢せず、早めに専門医に相談することが大切です。
ドケルバン病の診断と検査
あおと整形外科クリニックでは、ドケルバン病の診断のため、まず患者様から症状について詳しくお話を伺います。いつから、どのような時に、どのくらいの痛みがあるのか、仕事や趣味、育児で手を使う頻度などを確認します。
次に、手首の視診と触診を行い、痛みのある部位の腫れや圧痛(押した時の痛み)の有無を確認します。 ドケルバン病の診断に特徴的な検査として、「フィンケルシュタインテスト」があります。
フィンケルシュタインテスト
- 親指を他の指で包み込むようにして、軽く握りこぶしを作ります。
- そのまま手首を小指側にゆっくりと曲げます。
この時に、手首の親指側に強い痛みが生じれば、ドケルバン病の可能性が高いと判断されます。
また、必要に応じてX線(レントゲン)検査を行い、骨の異常や他の病気(関節炎など)がないかを確認します。腱鞘や腱自体の状態を詳しく見るために、超音波(エコー)検査を行うこともあります。エコー検査は、リアルタイムで腱鞘の肥厚や腱の炎症の有無を確認でき、診断の補助や治療方針の決定に役立ちます。
これらの丁寧な診察と検査を通じて、ドケルバン病の状態を正確に診断し、患者様一人ひとりに最適な治療計画を検討していきます。
ドケルバン病の治療法:痛みを和らげ、再発を防ぐ
ドケルバン病の治療は、症状の程度や原因、患者様のライフスタイルに合わせて、様々な方法を組み合わせて行われます。基本的には手術をしない「保存療法」が中心となりますが、症状が改善しない場合には「手術療法」も選択肢となります。
1. 保存療法:まずは手首を休ませることから
① 安静と活動制限
最も基本的な治療法であり、最も重要なステップです。痛みの原因となっている手首や親指の使いすぎを避け、患部を安静に保つことが大切です。
- ◾️作業内容の見直し
- パソコン作業の姿勢やマウスの持ち方、スマートフォンの操作方法などを見直します。
- ◾️育児中の工夫
- 授乳クッションや抱っこ紐を工夫し、手首への負担を減らします。
- ◾️スポーツ活動の調整
- 痛みが強い間は、原因となるスポーツ活動を一時的に休止したり、練習量を減らしたりします。
② 装具やサポーターによる固定
手首や親指の動きを制限し、腱鞘への負担を軽減するために、装具(シーネ)やサポーターを使用します。これにより、患部を安静に保ち、炎症の悪化を防ぐことができます。
③ 薬物療法
- ◾️内服薬
- 炎症を抑え、痛みを和らげるために、非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs)を処方することがあります。
- ◾️外用薬
- 湿布や塗り薬(消炎鎮痛剤の軟膏やゲル)を患部に貼ったり塗ったりして、局所の炎症を抑えます。
④ 注射療法(ステロイド注射)
保存療法の中でも、特に効果が期待できるのが、腱鞘内に直接ステロイド剤と局所麻酔薬を注入する治療です。ステロイドには強力な抗炎症作用があり、腱鞘の炎症を効率的に抑えることができます。 多くの場合、1回の注射で数週間から数ヶ月にわたって痛みが軽減し、そのまま治癒に至ることも少なくありません。ただし、ステロイド注射は頻繁に行うと、腱が脆くなるなどの副作用のリスクがあるため、医師の判断のもと、適切な間隔と回数で行われます。あおと整形外科クリニックでは、痛みの状態を詳しく診察し、患者様と相談しながら、注射療法の適応を慎重に判断いたします。
⑤ リハビリテーション(運動療法)
痛みが落ち着いてきたら、再発予防と機能改善のためにリハビリテーションを行います。国家資格を持つ理学療法士が、患者様一人ひとりの状態に合わせた運動療法を指導します。
- ◾️ストレッチ
- 硬くなった前腕の筋肉や手首、親指のストレッチを行い、柔軟性を高めます。
- ◾️筋力トレーニング
- 手首や指の安定性を高めるための軽い筋力トレーニングを行います。
- ◾️動作指導
- 日常生活や仕事、スポーツにおける手首や親指の負担を減らすための正しい体の使い方や動作の工夫を指導します。
- ◾️ハイドロリリース(筋膜リリース)
- 腱鞘炎の周囲の筋肉や筋膜が硬くなっている場合、超音波エコーガイド下でハイドロリリースを行うことで、筋肉の滑走性を改善し、痛みの軽減や可動域の改善を図る場合があります。
これらのリハビリテーションは、単に痛みを和らげるだけでなく、根本的な原因にアプローチし、再発しにくい身体づくりを目指します。
⑥ 物理療法
血行を促進し、炎症を抑え、痛みを和らげるために、様々な物理療法を行います。あおと整形外科クリニックでは、運動器リハビリの補助として機器を用いた物理療法を提供しています。
2. 手術療法:保存療法で改善しない場合
保存療法を数ヶ月続けても症状が改善しない場合や、痛みが繰り返し再発して日常生活に大きな支障をきたす場合には、手術療法が検討されます。
手術は、狭くなった腱鞘を切開し、腱がスムーズに動くようにするものです。通常、局所麻酔で行われ、手術時間は比較的短時間で済みます。最近では、超音波エコーガイド下で小さな切開から行う低侵襲な手術方法も行われることがあります。
手術後は、しばらく安静期間を設けた後、リハビリテーションを行い、手首の機能回復を目指します。手術により、多くの場合、痛みが劇的に改善し、日常生活や仕事、スポーツへの復帰が可能になります。
ドケルバン病の予防と日常生活での注意点
ドケルバン病を予防し、再発を防ぐためには、日常生活での工夫が非常に重要です。
- ◾️手首や親指の使いすぎに注意
- 特定の動作を長時間繰り返さないよう、こまめに休憩を取りましょう。
- ◾️正しい姿勢と動作
- パソコン作業では、手首が不自然に曲がらないよう、キーボードやマウスの位置を調整しましょう。
- ◾️適切な道具の使用
- クッション性のあるマウスパッドや、手首をサポートするサポーターなどを活用するのも良いでしょう。
- ◾️ストレッチの習慣化
- 日頃からふくらはぎや前腕、手首のストレッチを行い、筋肉の柔軟性を保ちましょう。
- ◾️育児中の工夫
- 赤ちゃんを抱っこする際は、手首だけでなく、腕全体や体幹を使って抱えるように意識しましょう。授乳クッションや抱っこ紐を積極的に利用することも大切です。
- ◾️痛みを我慢しない
- 少しでも痛みを感じたら、無理をせず、早めに医療機関を受診しましょう。早期に治療を開始するほど、回復も早まります。
ドケルバン病は、つらい痛みですが、適切な診断と治療、そして日頃のケアによって、多くの方が痛みから解放され、快適な日常を取り戻すことができます。手首の痛みでお悩みでしたら、一人で抱え込まず、あおと整形外科クリニックにご相談ください。私たちは、あなたの痛みに寄り添い、最適な治療とサポートを提供いたします。
FAQ
Q1:ドケルバン病は自然に治りますか?
A1:軽症の場合や、原因となる動作を完全にやめられる場合は、自然に治ることもありますが、多くの場合、痛みが慢性化しやすい傾向があります。特に、育児中の方や手を使う仕事の方は、痛みの原因となる動作を完全に避けることが難しいため、放置すると症状が悪化し、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。痛みが続く場合は、早めに整形外科を受診することをおすすめします。
Q2:ドケルバン病の注射は痛いですか?何回まで打てますか?
A2:注射の際には、局所麻酔薬も一緒に注入するため、一般的には「歯医者さんの麻酔注射くらいの痛み」と表現されることが多いです。注射後、一時的に痛みが強くなることもありますが、通常は数日以内に和らぎます。ステロイド注射の回数に明確な制限はありませんが、腱が弱くなるなどの副作用のリスクを考慮し、医師が慎重に判断します。通常は、数ヶ月の間隔を空けて、数回までが目安とされています。
Q3:ドケルバン病の治療で、サポーターやテーピングは効果がありますか?
A3:はい、サポーターやテーピングは、手首や親指の動きを制限し、腱鞘への負担を軽減する効果が期待できます。特に、痛みが強い急性期や、どうしても手を使わなければならない場合に有効です。ただし、長期間固定しすぎると、かえって手首が硬くなることもあるため、医師や理学療法士の指導のもと、適切に使用することが大切です。
Q4:ドケルバン病の予防のために、日常生活でできることはありますか?
A4:手首や親指の使いすぎを避け、こまめに休憩を取ることが重要です。パソコン作業では、手首が不自然に曲がらないよう、キーボードやマウスの位置を調整しましょう。育児中の方は、授乳クッションや抱っこ紐を工夫し、手首への負担を減らすことが大切です。また、日頃から手首や前腕のストレッチを行い、筋肉の柔軟性を保つことも予防に繋がります。
Q5:ドケルバン病と診断されたら、手術が必要になりますか?
A5:ドケルバン病の治療は、まず安静や薬物療法、装具による固定、注射療法、リハビリテーションなどの「保存療法」から始めます。これらの保存療法で多くの方が改善します。しかし、数ヶ月間保存療法を続けても痛みが改善しない場合や、痛みが繰り返し再発して日常生活に大きな支障をきたす場合には、手術療法が検討されます。手術は、狭くなった腱鞘を切開して腱への圧迫を取り除くもので、多くの場合、良好な結果が得られます。
📚 参考文献
- ドケルバン病(狭窄性腱鞘炎)|日本整形外科学会 症状・病気をしらべる https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/de_quervain_disease.html
- 腱鞘炎(ドケルバン病) | 慢性痛治療の専門医による痛みと身体のQ&A – オクノクリニック
- https://okuno-y-clinic.com/itami_qa/kensyouen.html
- 腱鞘炎の注射治療における痛み・効果・副作用を医師が解説 | リペアセルクリニック東京院
- https://fuelcells.org/topics/53021/
🔖 監修者情報
監修:日本整形外科学会専門医 青戸 寿之(あおと整形外科クリニック 院長)