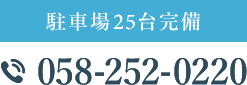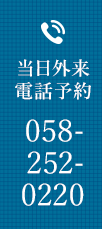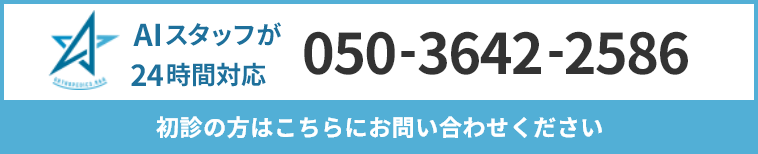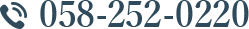お子さんが「かかとが痛い」と訴えたり、運動後に足をかばうように歩いたりしていませんか?特に、活発にスポーツをしているお子さんの場合、そのかかとの痛みは「シーバー病」かもしれません。シーバー病は、成長期の子ども特有の足のトラブルで、適切なケアを行うことで痛みを和らげ、安心してスポーツや日常生活を続けられるようになります。
もし、お子さんのかかとの痛みでお悩みでしたら、私たち整形外科がその不安に寄り添い、サポートいたします。あおと整形外科クリニックでは、お子さんの成長と活動を妨げないよう、丁寧な診断と一人ひとりに合わせた治療計画で、健やかな成長を応援しています。
シーバー病(踵骨骨端症)とは?なぜ成長期の子どもに多いの?
シーバー病は、正式には「踵骨骨端症(しょうこつこったんしょう)」と呼ばれ、主に8歳から15歳くらいの成長期にある子どもに多く見られるかかとの痛みです。特に活発な男の子に多い傾向があります。
なぜこの時期に発症しやすいのでしょうか?それは、子どもの骨が成長する過程に秘密があります。 大人の骨は一体ですが、子どもの骨にはまだ「骨端線(こったんせん)」、または「成長軟骨板」と呼ばれる柔らかい部分があります。かかとの骨(踵骨)にもこの骨端線が存在し、ここから骨が伸びて成長していきます。
しかし、この成長軟骨板は、まだ成熟した骨のように強くありません。この時期に、ランニングやジャンプなど、かかとに繰り返し強い衝撃や負担がかかると、アキレス腱や足の裏の腱膜(足底腱膜)が骨端線を引っ張り、小さな損傷や炎症を引き起こしてしまうのです。これがシーバー病のメカニズムです。例えるなら、まだ柔らかい成長途中の骨に、強い力が集中してかかり続けることで、痛みが生じる状態と言えるでしょう。
シーバー病の主な原因
シーバー病は、単一の原因で発症することは少なく、いくつかの要因が組み合わさって発症することがほとんどです。
- ◾️過度な運動量
サッカー、バスケットボール、陸上競技、バレーボールなど、走る・跳ぶ動作が多いスポーツをしている子どもに特に多く見られます。練習量や試合が多いと、かかとへの負担が蓄積されやすくなります。 - ◾️アキレス腱やふくらはぎの筋肉の柔軟性不足
- 成長期には、骨が急激に伸びる一方で、筋肉や腱の成長が追いつかないことがあります。特にふくらはぎの筋肉(腓腹筋、ヒラメ筋)やアキレス腱が硬いと、かかとの骨端線への牽引力が強くなり、負担が増加します。
- ◾️足の構造的な問題
- ・扁平足(へんぺいそく)
- 足の裏のアーチが低く、地面に接する面積が広い状態です。衝撃吸収能力が低下し、かかとへの負担が増えやすくなります。
- ・ハイアーチ(甲高):逆にアーチが高すぎる場合も、衝撃吸収がうまくいかず、特定の部位に負担が集中することがあります。
- ・不適切な靴
- クッション性が低い靴、かかとのホールドが不安定な靴、サイズが合わない靴なども、かかとへの衝撃を吸収しきれず、症状を悪化させる原因となります。
- ・急激な体重増加
- 体重が増えると、当然ながら足にかかる負担も大きくなります。
シーバー病の主な症状
シーバー病の代表的な症状は、かかとや足の裏の痛みです。
- ◾️運動時や運動後の痛み
- 走ったり、跳んだりした時、特に運動後に、かかとの後ろ側や底の部分に痛みを感じます。
- ◾️歩き始めの痛み
- 朝起きて最初の一歩や、長く座っていた後に立ち上がった時に、かかとが痛むことがあります。動き出すと痛みが和らぐこともありますが、これは足底腱膜炎と共通する特徴でもあります。
- ◾️かかとを押すと痛い(圧痛)
- かかとの後ろや底の部分、特にアキレス腱がかかとの骨に付着しているあたりを押すと強い痛みを感じます。
- ◾️つま先歩きになる
- 痛みを避けるために、無意識のうちにかかとを地面につけず、つま先で歩くようになるお子さんもいます。
- ◾️かかとの軽い腫れ
- 痛みのある部位に、わずかな腫れが見られることがあります。
これらの症状は、お子さんの運動能力を低下させるだけでなく、日常生活にも影響を与えることがあります。痛みを我慢させたり、「成長痛だから仕方ない」と放置したりせずに、早めに専門医に相談することが大切です。
シーバー病の診断と検査
あおと整形外科クリニックでは、お子さんのかかとの痛みに対し、日本整形外科学会専門医である院長が丁寧に診察を行います。
まず、お子さんや保護者の方から、いつから、どのような時に、どのくらい痛むのか、どのようなスポーツをしているのか、運動量や頻度はどのくらいかなどを詳しくお伺いします。次に、足の視診と触診を行い、かかとのどの部分に痛みがあるのか、腫れや熱感の有無、足のアーチの形、足首やふくらはぎの柔軟性などを細かく確認します。
診断の確定には、画像検査が重要です。
- ◾️X線(レントゲン)検査
- かかとの骨端線(成長軟骨板)の状態や、骨の異常がないかを確認します。シーバー病の場合、骨端線が不規則に見えたり、骨が分節しているように見えたりすることがあります。また、他の骨の病気や骨折の可能性を除外するためにも重要です。
- ◾️超音波(エコー)検査
- 必要に応じて、超音波エコー検査を行うこともあります。エコー検査は、骨端線周辺の炎症やむくみ、アキレス腱の状態などをリアルタイムで詳しく観察でき、診断の補助として役立ちます。
これらの丁寧な診察と検査を通じて、シーバー病の状態を正確に診断し、お子さん一人ひとりに最適な治療方針を検討していきます。
シーバー病の対処法・治療法
シーバー病の治療は、基本的に手術を必要としない「保存療法」が中心となります。お子さんの痛みを和らげ、安全に活動を再開できるよう、様々な方法を組み合わせて行います。
1. 安静と活動制限:最も重要なステップ
痛みの原因となっている運動を一時的に制限し、かかとへの負担を減らすことが何よりも大切です。痛みが強い間は、ランニングやジャンプを伴うスポーツ活動を控え、安静を保つようにします。完全に運動を中止する必要がない場合でも、練習量や強度を調整するよう指導します。
2. アイシング:炎症を抑える
運動後や痛みが強い時には、氷嚢や保冷剤をタオルで包んで、かかとの痛む部分に15~20分程度当てて冷やします。これにより、炎症を抑え、痛みを和らげる効果が期待できます。
3. ストレッチとマッサージ:柔軟性の向上
硬くなったふくらはぎの筋肉やアキレス腱、足底腱膜の柔軟性を高めるストレッチは、かかとへの負担を軽減するために非常に重要です。
- ふくらはぎのストレッチ:壁に手をつき、痛い方の足を後ろに引いて、かかとを地面につけたまま、ふくらはぎをゆっくり伸ばします。
- 足底腱膜のストレッチ:ゴルフボールやテニスボールを足の裏で転がしてマッサージしたり、つま先を手で持って足の裏を伸ばしたりします。 理学療法士が、お子さんの身体の状態に合わせた効果的なストレッチやマッサージの方法を丁寧に指導します。
-
4. 靴の見直しとインソールの使用
クッション性が高く、かかとをしっかりと包み込み、安定性のあるスポーツシューズや普段履きの靴を選ぶことが大切です。 また、かかとの負担を軽減するために、「ヒールカップ」や「かかとを高くするインソール(足底板)」を使用することが有効です。これらは、かかとへの衝撃を吸収したり、アキレス腱の牽引力を和らげたりする効果が期待できます。あおと整形外科クリニックでは、お子さんの足の形や症状に合わせた靴選びやインソールの活用について具体的なアドバイスを行っています。
5. 理学療法・リハビリテーション
国家資格を持つ理学療法士が、お子さんの身体の使い方や動きの癖を評価し、適切なリハビリテーションメニューを作成します。
- ◾️運動療法
- 足首や足の指の筋力強化、バランス能力の改善、正しい歩き方や走り方の指導などを行います。
- ◾️姿勢の改善
- 姿勢の偏りや、体幹の不安定さが原因となることもあるため、全身のバランスを整える指導も行います。
6. 物理療法
痛みの軽減や組織の回復を促すために、運動器リハビリの補助として物理療法を行います。血行促進、炎症の抑制、痛みの緩和を図ります。
シーバー病の治療は、痛みがなくなるだけでなく、再発を防ぐためのケアが重要です。リハビリテーションを通じて、柔軟性、筋力、そして運動のフォームを改善することで、お子さんが安心してスポーツを続けられる身体づくりを目指します。
焦らず、お子さんの成長を待つことが大切
シーバー病は、成長期の骨の構造が原因で起こるため、基本的には成長が終われば自然と治癒することがほとんどです。しかし、それまでの間、痛みを我慢させたり、不適切な対処を続けたりすると、痛みが長引いたり、歩き方や姿勢に悪影響が出たりする可能性があります。
大切なのは、お子さんの痛みに寄り添い、焦らずに適切な治療とケアを続けることです。もし、お子さんのかかとの痛みでお悩みでしたら、一人で抱え込まず、まずはあおと整形外科クリニックにご相談ください。お子さんの健やかな成長を、専門医と理学療法士が全力でサポートいたします。
FAQ
Q1:シーバー病は「成長痛」とは違うのですか?
A1:一般的な「成長痛」は、夜間に足の痛みを訴えることが多く、痛みがある場所が一定せず、日中には痛みが消えることが多いのが特徴です。一方、シーバー病は、かかとの特定の場所(踵骨骨端線部)に痛みが集中し、運動や活動によって痛みが悪化するのが特徴です。シーバー病は成長期のスポーツ障害の一種と捉えるべき疾患で、適切な治療が必要です。
Q2:シーバー病はどれくらいの期間で治りますか?
A2:症状の程度や個人差はありますが、多くの場合、適切な治療と安静期間を設けることで、痛みが数週間から数ヶ月で改善に向かいます。完全に痛みがなくなり、成長軟骨が成熟するまでには数ヶ月から1年程度かかることもあります。お子さんの成長が終わる頃には自然に治癒することがほとんどですが、それまでの間、痛みをコントロールしながら、根気強くケアを続けることが大切です。
Q3:シーバー病と診断されても、スポーツを続けても大丈夫ですか?
A3:痛みが強い間は、痛みの原因となっている運動(特にランニングやジャンプ)を控えることが非常に重要です。無理をして運動を続けると、炎症が悪化し、治癒が遅れる可能性があります。痛みが和らいでからは、徐々に運動を再開していきますが、練習量や強度、そして運動フォームに注意が必要です。当クリニックでは、お子さんの状態に合わせて、無理なくスポーツを続けられるようアドバイスを行います。
Q4:自宅でできるシーバー病のケアはありますか?
A4:はい、いくつかあります。まず、運動後や痛む時にかかとを冷やす「アイシング」が有効です。次に、ふくらはぎの筋肉やアキレス腱、足の裏の柔軟性を高める「ストレッチ」をこまめに行いましょう。また、クッション性の高い靴を選んだり、かかとを保護するインソールを使用したりすることも大切です。具体的なストレッチ方法やケア用品については、診察時に理学療法士が詳しくお伝えします。
Q5:シーバー病は大人になってから後遺症が残ることはありますか?
A5:シーバー病は、成長期に起こる一時的な炎症であり、骨の成長が完了し、骨端線が閉じるとともに自然に治癒するため、大人になってから後遺症が残ることはほとんどありません。ただし、適切な治療やケアを怠り、痛みを我慢し続けた場合、一時的にかかとの骨が変形したり、痛みが長引いたりすることはありえます。早期に専門医に相談し、適切な対処をすることが大切です。
📚 参考文献
- ▪️踵骨骨端症(シーバー病) 日本整形外科学会 症状・病気をしらべる https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/calcaneal_apophysitis.html
- ▪️シーバー病(踵骨骨端症)とは? | 治療法・原因・症状を解説 – リペアセルクリニック
https://fuelcells.org/topics/59389/ - ▪️シーバー病(踵骨骨端症) – 公益財団法人日本学校保健会
https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H28/html5.html#page=38 -
📚監修者情報
監修:日本整形外科学会専門医 青戸 寿之(あおと整形外科クリニック 院長)